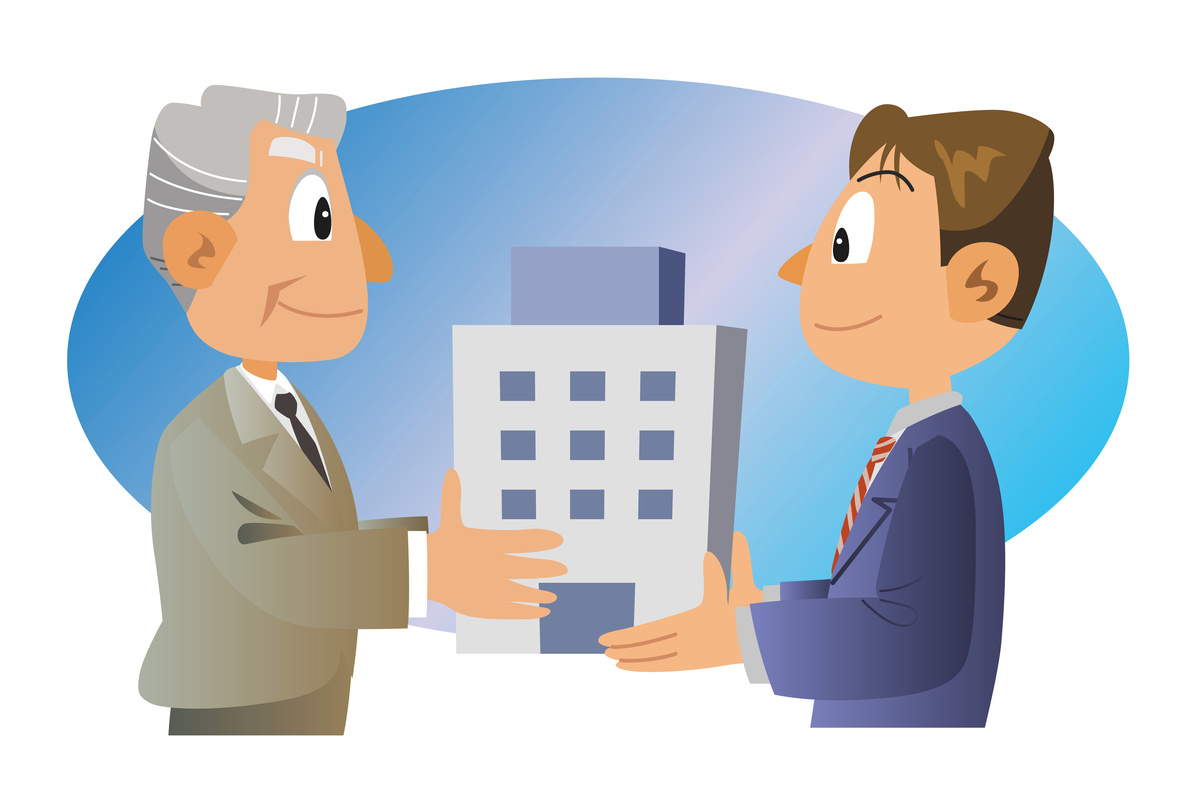目次
事業承継は終わりではなく、会社の新たな始まりです。しかし、親族に継がせるべきか、従業員に託すべきか、それともM&Aという選択肢が良いのかなど、迷いや不安を抱える経営者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、中小企業が直面する課題にリアルに向き合い、事業承継を成功させた事例をタイプ別に紹介します。自社に近い事例を知ることで、「自分の会社でもできるかもしれない」と思えるヒントになれば幸いです。
事業承継を円滑に進めるためには、後継者に「どのような組織を引継ぎたいと思ってもらえるか」も大切な視点です。
株式会社メタメンターの「ウェルビーイング診断」は、従業員のウェルビーイング(心理的、社会的、身体的に満たされた状態を表す概念)を数値化できます。
組織の雰囲気や課題を客観的に可視化することで、後継者が不安なく引継ぐ組織の基盤づくりを支援する「ウェルビーイング診断」は下記から気軽にお試しください。
事業承継3つのタイプとメリット・デメリット

事業承継のタイプは、大きく下記の3つです。
各タイプの特徴を理解し、自社の状況や目的に合った承継方法を選ぶためには、メリットとデメリットを押さえておくことが重要です。
ここからは、それぞれのタイプのメリット・デメリットを整理してご紹介します。
なお下記の記事では、継承との違いや経営者・後継者それぞれが直面しやすい課題と解決策など事業承継について網羅的に紹介しています。併せてご覧ください。

事業承継とは?3つの要素や継承との違い・立場別の課題と成功へ導くポイントを紹介
事業承継に悩む経営者・後継者必見!本記事では、事業承継の基本や3つの要素・主な承継手法の他、経営者・後継者が直面する課題とその解決策、活用できる支援制度も紹介します。
記事掲載日:2025年6月24日
タイプ1.親族内での事業承継
親族内承継は、経営者の子どもや孫、兄弟など、親族に会社を引継ぐ方法です。
【メリット】
・会社の文化や理念が引継がれやすく、従業員や取引先も安心しやすい
・相続税対策など、税制面で有利になる場合もある
【デメリット】
・後継者候補がいない、あるいは後継者に経営の意思や能力がない場合に難しい
・他の親族との間で意見の食い違いが生じるおそれもある
「信頼を引継ぐ」形での承継ができる一方、親族内に適任者がいない場合の選択肢は限られるため、早期に意思確認と育成を始める点がポイントです。
タイプ2.従業員への事業承継
従業員承継は、長年会社を支えてきた役員や従業員に会社を譲る方法です。
【メリット】
・会社の内部事情をよく知る人物が引継ぐため、スムーズに経営を継続できる
・従業員のモチベーション向上にもつながる
【デメリット】
・後継者となる従業員に資金力がない場合がある
・個人保証の引継ぎなど、金融機関との調整が必要になるケースもある
社内に理解のある人材がいる場合は有力な選択肢ですが、経営者としての視座を持たせる教育と支援が不可欠です。
タイプ3.M&Aによる第三者への事業承継
M&A(企業の合併・買収)による第三者承継は、他の企業や個人に会社を売却する方法です。
【メリット】
・後継者が見つからない場合でも事業を継続できる
・売却益を得て、引退後の生活資金に充てられる
・買い手の持つ経営資源を活用し、事業をさらに拡大できる可能性もある
【デメリット】
・会社の文化や従業員の雇用維持が難しくなる場合がある
・条件交渉が難航すると、売却に時間がかかる
「売却=終わり」ではなく、「企業の命をつなぐ選択肢」として前向きにとらえることが大切です。信頼できる専門家の仲介やマッチング支援の活用がポイントとなります。
タイプ別!事業承継の成功事例8選

事業承継にはさまざまな形があり、どの方法が自社に合っているか迷われる方も多いのではないでしょうか。
本章では、「親族内承継」「従業員承継」「第三者承継」の3つのタイプに分けて、具体的な成功事例をご紹介します。
まずは、自社と近いケースを見つけやすくするために、事例の一覧表をご覧ください。
【タイプ別事例一覧】
| タイプ | 事例名 | 特徴・学び |
|---|---|---|
| 親族内 | 株式会社増田採種場 | 自然な意思形成 × 信頼関係 |
| 親族内 | 株式会社エーアイテック | 工場移転との同時推進 × 計画的OJT |
| 親族内 | 株式会社友安製作所 | 第二創業 × ブランド再構築 |
| 従業員 | 株式会社ユニックス | アンケートで選出 × 納得感 |
| 従業員 | 株式会社朝日山洋服店 | 元取引先社員を抜擢 × 信頼関係 |
| 第三者 | 有限会社平船精肉店 | 味と雇用の継続 × 公的支援の活用 |
| 第三者 | 有限会社ショッピング | 地域スーパー × 地方移住者とのマッチング |
| 第三者 | 株式会社さらい(美容室Cut Roze) | 地域貢献 × 移住者による再建 |
「親族内承継」からみていきましょう。
親族内の事業承継による成功事例

家族間の信頼を土台に、理念や文化を自然に受け継いだ成功事例を紹介します。次世代の挑戦や組織変革がどう実現されたのかに注目してご覧ください。
【本事例は、特にこんな人におすすめ】
・親族への事業承継を前向きに検討している経営者・後継者
・親子・家族間で無理なく信頼関係に基づいた承継を進めたい方
・承継をきっかけに、組織の風土や未来志向の文化を育てたい方
・第二創業や新たな事業展開を見据えている後継者
事例1.自然な形で受け継がれた創業100年のバトン
1925年創業の老舗種苗会社、株式会社増田採種場は、アブラナ科野菜の品種開発から生産、販売までを一貫して手がける企業です。
【承継の背景・プロセス】
・息子の雄紀氏は、別業界での社会人経験を経て、家業と両親へのリスペクトから入社
・幼少期から畑に親しみ、自然と「継ぎたい」という思いが芽生えていた
・専務である増田氏は息子に「継いでほしい」と一度も押し付けることなく、本人の意思を最優先
・どちらも「事業承継」「後継ぎ」という言葉自体がしっくりこないほど、自然なかたちでバトンパスがおこなわれている
【成功のポイント・学び】
・親子間の信頼関係をベースに、自然な意思で承継
・「継いでほしい」と押しつけない姿勢が、主体的な承継意欲を育んだ
・承継後の組織づくりにおいては、社内だけで抱え込まず、外部の支援者とともに未来を見据える対話の場を設けたことで、部署を超えた共通認識と行動宣言が生まれた
本事例では親子の信頼関係と、外部の力を借りた組織全体の未来像共有が、自然で主体的な親族内承継を可能にすることを示しています。
増田採種場では、親族内での自然な承継に加え「ストーリー年表」を通じて社員全員で未来を語り合う組織文化を育てています。導入の経緯や成果は、以下のインタビュー記事で詳しくご紹介しています。

視座を高め社員と未来を語る場を!「ストーリー年表」で描く組織の未来像
部署を超えた対話で未来への視座を高め、AI活用への理解も促進したという増田採種場。この記事では、メタメンターの「ストーリー年表(未来編)」の効果を紹介します。
記事掲載日:2025年8月18日
事例2.工場移転と事業承継を一体化
長野県松本市に拠点を置くFA(Factory Automation)機器の開発・設計・製造・販売を手がける株式会社エーアイテックは、工場移転と事業承継を同時に推し進めることで、会社の刷新と大幅な成長を遂げました。
【承継の背景・プロセス】
・現社長・大林泰彦氏は、IT企業でエンジニアとして勤務していた2006年、父である先代社長から承継の打診を受けた
・当初は断ったものの、会社の技術力や社員の雰囲気に惹かれ、2008年に入社
・業務理解のため営業・製造・設計をOJTで習得し、3DCADや社内システムの刷新などにも挑戦
・2014年、既存の6倍の面積を持つ新工場への移転を機に、業務の見える化とリーダーシップ移行を加速させ、2017年に社長に就任。事業承継前と比較して、売上は2倍、営業利益は4倍に伸長した
【成功のポイント・学び】
・工場移転のような大きな経営課題を、事業承継を推進する絶好の機会ととらえ、同時に実行することで相乗効果を生み出す
・段階的な役割移行により、従業員への信頼と自然な承継を実現
・業務改革や働き方改善を通じて、売上2倍・営業利益4倍に成長
・入社から就任まで約10年。長期スパンでの育成が成果につながった
株式会社エーアイテックの事例は、事業承継をきっかけに、業務改革と成長を同時に実現した好例です。
参考:事例ナビ「工場の移転拡張を契機に事業承継を推進し、会社の刷新と成長を遂げる企業」|経済産業省
事例3.第二創業をきっかけに、従業員6名から86名へ
大阪府八尾市の株式会社友安製作所は、カーテンレールやフロアタイルなどのインテリア製品や業務用資材の加工・輸入販売をおこなう企業です。
「安くて手軽にDIYを楽しめる商材の提供」をコンセプトに、DIYの魅力を顧客に体感してもらうことを目指しています。
【承継の背景・プロセス】
・創業以来、木製ねじ→線材加工→インテリア資材と業態変化するも、2000年代には従業員が6名まで減少
・現代表・友安啓則氏が米国での事業経験を経て2004年に帰国し、社員として入社
・父である先代社長とは別の事業の立ち上げ(第二創業)を約束し、月15万円の予算でDIY商材販売を開始
・自作のWebサイトで台湾製品を販売 → 初回完売 → ブランド「COLORS」立ち上げ
【成功のポイント・学び】
・「安く、手軽にDIYを楽しめる商材の提供」のコンセプトに基づいて事業を再構築
・少額予算からスタートし、ネット販売と独自ブランドで顧客を獲得
・「体験と共感」を軸に、カフェ・コンセプトショップ・住宅コラボなど多チャネル展開
・6名→86名へと社員数が14倍に。社内外の信頼を再構築しながら、会社を再生・拡大している
株式会社友安製作所の事例は、承継を機に新たな価値を打ち出し、再成長へとつなげた第二創業型の成功パターンです。
参考:第二創業をきっかけとして、明確な事業コンセプトの下に、経営再建に成功した企業|ミラサポplus|経済産業省
従業員への事業承継による成功事例

親族以外でも、社内の信頼できる人材への承継で事業を発展させた事例があります。
従業員の意欲や外部支援の活用がポイントとなったケースをみていきましょう。
【本事例は、特にこんな人におすすめ】
・親族内に後継者が見つからず、従業員承継を検討している経営者
・従業員の納得感を得ながら事業承継を進めたい方
・事業承継ファンドの活用を考えている方
事例1.全従業員アンケートで後継者を選定
大阪府東大阪市の株式会社ユニックスは、1984年設立の表面処理加工業を営む企業です。
ポリウレタンの表面処理技術を強みに、研究開発型企業として長年事業を展開してきました。
【承継の背景・プロセス】
・創業者の苗村会長が高齢となり、事業承継を検討
・親族内に適任者がいなかったため、従業員への承継を決意
・全従業員を対象としたアンケートで「次の社長にふさわしい人物」を尋ねたところ、全員が町田氏を推薦
・苗村会長の意中とも一致し、町田氏を後継者に内定(当初は辞退も、1年間の説得で受諾)
・3年間の準備期間中に経営を学び、2016年に社長就任(代表権なし)→ 2020年に代表取締役へ
【成功のポイント・学び】
・従業員の意見を取り入れた後継者選定で、納得感と一体感が醸成された
・経営者育成の準備期間(3年間)を確保したことで、スムーズな移行が実現
・議決権の設計に「事業承継ファンド」を活用し、株式移転も無理なく進行
・新社長の下、粉体関連市場への販路拡大を進行中
株式会社ユニックスの事例は「従業員からの選出 × 段階的な移行 × 外部支援の活用」という3要素がそろった好例です。
参考:従業員への事業承継に当たり、全従業員アンケートにより後継者を選定した企業|ミラサポplus|経済産業省
事例2.同業のすご腕営業経験者を社長に抜擢
大阪市で100年以上の歴史を持つ株式会社朝日山洋服店は、学生服販売を柱として地域に根差してきました。
3代目の佐々木義之社長は親族に後継者がいないなか、長年の取引先であり同業の「すご腕営業経験者」であった日高明伴氏を従業員として迎え入れ、社長としてバトンを渡すことに成功しています。
【承継の背景・プロセス】
・1904年創業の老舗学生服店。3代目・佐々木義之氏が高齢となり、親族内に後継者がいないことから、外部への承継を検討
・長年の取引先であった大手学生服メーカーの営業担当・日高明伴氏を「社長候補」という位置付けで従業員として招き入れる
・約3年間、社内業務や顧客・従業員との信頼関係を構築
・永和信用金庫の紹介で、大阪府事業承継・引継ぎ支援センターへ相談
・司法書士ら専門家の支援を得て、登記手続きや株式移転などの準備を整え、2021年1月に正式に社長へ就任
【成功のポイント・学び】
・従業員承継の準備期間を3年設け、スムーズな引継ぎを実現
・親族ではないが、長年の信頼関係が承継の基盤に
・地元の金融機関(永和信用金庫)の関与により、支援機関と専門家に迅速につながったことが後押しに
・既存従業員・顧客との関係性を壊さずに「人を中心にした事業承継」が成立
・あらかじめ「社長就任を前提とした採用」というステップを踏んだことが、周囲の納得感と社内の安定につながった
株式会社朝日山洋服店の事例は「信頼関係×現場理解×公的支援」の3軸で成功した、従業員承継の好例です。取引先の営業担当という立場から経営者へステップアップした稀有な事例であり、中小企業の人材を活かす承継の可能性を示すモデルケースといえます。
参考:〈事例14〉株式会社朝日山洋服店|従業員承継の事例紹介|事業承継・引継ぎポータルサイト
M&Aによる第三者への事業承継による成功事例

ここからは「売却=終わり」ではなく、会社の新たな命をつなぎ、活性化させた成功事例を紹介します。
【本事例は、特にこんな人におすすめ】
・親族や従業員に後継者が見つからず、第三者承継を検討している経営者
・地域密着型の事業を、想いや価値ごと次世代に引継ぎたい方
・M&Aで事業の存続・発展を目指したいと考えている方
・信頼できる外部支援を活用して、安心して承継を進めたい方
事例1.M&Aで地域に愛される精肉店を承継
有限会社平船精肉店は、岩手県で長年地域に親しまれてきた精肉店です。
創業者の平船氏が70歳を超え、親族にも従業員にも後継者が見つからないなか、事業引継ぎ支援センターを活用し、独立を希望する個人への事業承継を通じて、屋号・味・従業員の雇用を守ることに成功しました。
【承継の背景・プロセス】
・70代の創業者・平船氏が高齢化を機に承継を検討
・親族・従業員ともに後継者不在
・地元で親しまれていた店舗と味、雇用を残したいという思いから、第三者への譲渡を決断
・最初はM&A仲介会社を活用するも不成立
・岩手県事業引継ぎ支援センターの紹介により、経営未経験の竹林誠氏とマッチング
・承継条件は「屋号・味・雇用の継続」
【成功のポイント・学び】
・公的支援機関(事業引継ぎ支援センター)の活用で信頼性の高いマッチングが実現
・屋号・商品・雇用の明確な譲渡条件が買い手の安心感に
・3ヵ月の現場引継ぎ+その後の顧問支援でスムーズに事業が継続
・経営未経験者でも、支援機関のフォローによりM&Aが可能
有限会社平船精肉店の事例は「地域密着型の店舗」でもM&Aが機能する好例です。買い手が個人であっても、適切な支援と丁寧な引継ぎがあれば事業は持続可能であることがわかります。
参考:事業引継ぎ支援センターを介し、独立を希望する個人に事業を引き継いだ企業より」ミラサポplus|経済産業省
事例2.地域スーパーが首都圏からの移住者へ承継
徳島県海陽町の有限会社ショッピングは、1970年から地域に密着したスーパーマーケットを運営してきました。
後継者が見つからず、廃業の瀬戸際にあるなか、地域への強い思いを持つ首都圏からの移住者へ事業を承継し、新たな形で地域に貢献しています。
【承継の背景・プロセス】
・高齢・健康不安を理由に、60代で廃業を検討していた大黒会長
・地域の買物インフラ喪失による影響を危惧し、第三者承継を決断
・海陽町への移住者・岩崎氏と神社での活動を通じて偶然出会う
・自然食販売の夢と地域貢献の理念が一致
・徳島県事業引継ぎ支援センターの全面的支援を受け、わずか5ヵ月で承継完了
【成功のポイント・学び】
・理念の一致と地域課題への共感が、スムーズな承継の決め手に
・支援センターのバックアップにより、短期間で実現
・従業員全員を継続雇用+移住者も新規採用し、雇用を倍増(8名→18名)
・高付加価値商品(無添加総菜、オーガニックワイン)を軸に新たな需要を創出
・EC・直営カフェ・自社ブランドなど、次の展開にも意欲的
有限会社ショッピングの事例は「地域の生活インフラ×移住者の夢×公的支援」の好循環によって成功した、第三者承継のモデルケースです。「地方企業の承継=縮小」ではなく、「成長の再起点」になり得ることを示しています。
参考:令和2年度 中小企業・小規模事業者及び支援機関等における 優良取組事例に関する調査事業|経済産業省
事例3.美容室を地域に残したい想いがエリアを超えて実現
千葉駅近くに店を構える低価格型美容室「Cut Roze(カットロゼ)」を運営する株式会社さらい(前社長:村田正一郎氏)は、顧客サービスと従業員の雇用を守るため、2つの事業承継・引継ぎ支援センターの連携を通じて、最適な後継者へ事業を承継しました。
【承継の背景・プロセス】
・多事業展開していた村田前社長、60歳を過ぎて引退と事業承継を意識
・飲食店は親族に承継したが、美容室は親族・従業員への承継が困難で廃業も検討
・「顧客と従業員の生活を守りたい」と、千葉県事業承継・引継ぎ支援センターへ相談
・千葉県内での後継者が見つからず、東京都のセンターと連携して候補者を探索
・元・大手美容室チェーン経営者である佐藤氏と面談・意気投合し、5ヵ月で承継完了
【成功のポイント・学び】
・「顧客サービスと雇用を守る」という理念に共感した譲受者との出会いがポイント
・千葉県・東京都の広域連携による支援センターのマッチング体制が有効に機能
・譲渡者が承継条件(雇用維持・サービス継続)の明確さがスムーズな交渉を後押し
・引継ぎ後、従業員との信頼構築を最優先に経営を再スタート
・顧客・従業員・店舗という地域密着の価値を損なうことなく事業を継続
株式会社さらいの事例は、「地域の雇用・サービス×経営経験者の再挑戦×公的支援」の好循環が生んだ承継の成功例です。
参考:〈事例27〉株式会社さらい|第三者承継の事例紹介|事業承継・引継ぎポータルサイト
本事例のように、「想いを引継ぐ」第三者承継には、マッチングというアプローチもあります。マッチングのポイントや成功事例については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

後継者マッチングで事業承継を成功!中小企業向け完全ガイド【2024年版】
後継者マッチングで事業承継を成功させる!中小企業向けに仕組みや種類、事例を解説。後継者不足の課題を解決し未来を切り拓く!支援制度も紹介。
記事掲載日:2025年6月25日
事例から導き出す!事業承継を成功させる5つのポイント

これまで紹介してきた事例や中小企業庁の「事業承継ガイドライン」から、事業承継を成功させる主なポイントを5つ紹介します。
なかでも、最初に紹介する早期の準備と経営の見える化は、ガイドラインと複数の事例から導き出された押さえておきたい重要なポイントです。
ポイント1. 早期かつ計画的な準備
事業承継には5〜10年の準備期間が必要とされており、「いつかではなく今から」が鉄則です。
中小企業庁の「事業承継ガイドライン」でも「引退時期から逆算し、計画的に準備を始めること」が強調されています。
前章で紹介した株式会社エーアイテックでは、社長交代まで約10年をかけて段階的にOJTや業務改革を進め、自然なリーダーシップ移行を実現しました。
また、株式会社ユニックスのように3年間の準備期間を設け、経営の学びと社内の信頼形成を並行しておこなうことで、スムーズな承継が叶っています。
【早期かつ計画的な準備の例】
・「何歳で引退するか」を仮決めして逆算
・現社長と後継者の役割移行スケジュールを立案
・工場移転や新規事業など、大きな変化を承継とセットで設計すると効果的
事業承継の具体的な進め方については、以下の記事で詳しく解説しています。準備期間の目安から具体的なアクションプランまで、スムーズな事業承継を実現するための10ステップを紹介していますので、参考にご覧ください。

【中小企業向け】事業承継をスムーズに進める10のステップ|成功の鍵は早期準備
「事業承継 スムーズに進める方法」を解説。後継者不足でお悩みの経営者へ、早期準備と計画的な実行で事業承継を成功させる方法を紹介します。10のステップでスムーズな事業承継を実現しましょう!
記事掲載日:2025年6月9日
ポイント2.経営の見える化と棚卸し
経営資源の整理・可視化は、承継の「引継ぎやすさ」を左右します。
経営の見える化や棚卸しをする際は、属人化されたノウハウや関係性を洗い出して、経営情報・顧客データ・社内業務のフローなどを文書化・共有し、後継者の判断を助けることがポイントです。
例えば株式会社エーアイテックでは、CAD導入やシステム刷新を通じて業務の見える化を進めたことで、承継後の成長スピードが向上しました。
株式会社朝日山洋服店でも、3年間の準備期間中に業務習得や顧客対応の引継ぎを徹底し、現場理解に基づく承継を成功させています。
【見える化と棚卸しの例】
・財務・顧客・取引先・業務プロセスを棚卸し
・属人業務を「誰でもわかる」状態に
・定量データだけでなく定性情報(価値観・暗黙知)も整理
事業承継を円滑に進めるには、経営の見える化だけでなく、従業員のモチベーションや人間関係などの「組織の状態の可視化」も大切です。疲弊した組織では、後継者がどれだけ優秀でもスムーズな承継は難しいといえます。
このような見えにくい課題に対応するには、組織状態を客観的に把握できるツールの活用が有効です。そこでおすすめしたいのが、メタメンターの「ウェルビーイング診断」です。「ウェルビーイング診断」は、従業員の「心理的・社会的・身体的」な側面を統合的に評価・数値化できる診断ツールです。
例えば、下記のような場面で活用していただけます。
【ウェルビーイング診断の活用シーン例】
・従業員の状態を定量的にとらえたいときに
・モチベーションや人間関係の現状を把握したいときに
・組織の疲弊感や分断の兆候を早めに察知したいときに
・後継者が信頼関係を築くための現場理解を深めたいときに
早稲田大学人間科学学術院の大月教授(臨床心理士・公認心理師)監修のもと、学術的な知見に基づいて開発され信頼性が高い診断が得られる「ウェルビーイング診断」は下記からお試しください。
心理的・社会的・身体的と網羅的に評価!
ウェルビーイング診断はこちらポイント3.後継者の選定と育成
誰に引継ぐか、そしてどう育てるかは承継成功の核心です。中小企業庁も「後継者の意思確認と育成は最優先事項」と位置づけています。
冒頭で紹介した株式会社増田採種場では、現経営者が「継いでくれと言ったことがない」と語り、後継者である雄紀氏の主体的な承継意欲を尊重しました。幼少期から事業に触れるなかで自然に「継ぎたい」という気持ちが芽生え、親子の信頼関係をベースに、無理なくバトンが渡されています。
株式会社ユニックスのように従業員投票を通じて社長を選出したケースでは、「自分たちで選んだリーダー」という意識が共有され、社内の納得感と結束力が高まっています。
【成功のポイント】
・意思確認は早期に、無理強いせず対話を重ねる
・段階的に業務と意思決定の範囲を広げていく
・外部研修・支援機関の活用で経営者視点を養う
ポイント4.財務・税務・法務面の対策
「税金や株のことで承継が進まない」といった事態は、事業承継の典型的な失敗パターンの一つです。
財務・法務リスクを避けるためには、事業承継税制の活用や自社株評価の適正化、個人保証の整理などの事前対策が必要となるので、実施を検討しましょう。
例えば、株式会社ユニックスでは「事業承継ファンド」を活用して、議決権と株式の移転設計をスムーズにおこなっています。
株式会社朝日山洋服店でも、司法書士や信用金庫の支援を得て、登記や株式の手続きを着実に進めました。
【成功のポイント】
・税理士・弁護士・金融機関と早期に相談
・経営承継円滑化法・事業承継税制など制度の活用
・個人保証・借入金・役員報酬の整理を含めた包括的対策を
ポイント5. 第三者の支援活用
事業承継は経営者と後継者だけで完結する話ではありません。公的支援機関や専門家の助けを得ることで、視野が広がり、問題解決が進みます。
実際に有限会社平船精肉店や株式会社さらいなどのM&A事例では、事業引継ぎ支援センターのマッチング支援が決定的な役割を果たしています。
事業引継ぎ支援センター以外の第三者支援機関として挙げられるのが、信用金庫や地域の支援機関です。これらの介在により、安心感をもってプロセスを進めることができます。
【成功のポイント】
・「何を誰に相談するか」を整理する
・地域の商工会議所、事業引継ぎ支援センターなどの無料支援を活用
・金融・税務・M&Aの各専門家を適切にアサイン
経営者と従業員が、第三者の視点や専門的な知見を得ながら未来のビジョンをともに描き、共有する機会として、株式会社メタメンターのサービスは有用です。
特にファミリービジネスでは、「所有」「経営」に加えて「家族」という視点が絡むため、親と子、現経営者と後継者の間に認識のズレが生じやすく、事業承継の障壁となりがちです。
メタメンター代表である小泉は、こうした構造的な課題に対して「第三者によるチームコーチングが有効である」と述べています。外部の支援者の介入により、見えない力関係や価値観のすれ違いが整理されることで生まれるのが、経営者・後継者・幹部がともに未来を描くための一体感です。
ファミリービジネスにおける「見えない力関係」や「認識のズレ」にどう向き合うべきかなどのヒントを得たい方は、小泉が登壇したセミナーのレポートもぜひご覧ください。
参考:組織変革に悩む事業承継者向け「チームで伝統を引き継ぐリーダーシップ」 に関するログ一覧 | ログミーBusiness
認識のズレを乗り越えて、社内に次世代に向けた一体感を生み出すきっかけとなるチームコーチングですが、「興味はあるけれど、何から始めたらいいの?」「そもそも、コーチはどうやって探すの?」などの疑問があるのではないでしょうか。チームコーチングに関してご興味がある方は、国際コーチング連盟(ICF)認定PCCを有している小泉が代表をつとめるメタメンターに、下記からお気軽にお問い合わせください。
国際コーチング連盟(ICF)認定PCC取得者に相談できる!
コーチング導入に関するご相談はこちらまとめ:成功事例を活かし、自社ならではの承継の道を切り拓こう

事業承継の成功は役職の引継ぎだけではなく、「どのような組織を残したいか」「どのような未来をともに描きたいか」を共有することが大切です。
今回ご紹介した多様な成功パターンをヒントに、自社の強みや状況に合った承継のかたちを見つめ直し、計画的な準備へとつなげていきましょう。
もし、経営者と後継者、幹部が一体となって会社の未来を描くことに課題を感じているなら、株式会社メタメンターのサービスがおすすめです。
事業承継の過程で生じやすい「すれ違い」や「見えない力関係」を解消し、次世代に向けた強いチームを築くための対話や共通認識づくりをサポートします。
組織全体の一体感やコミュニケーションの質を高められるとご好評の「ストーリー年表」などのワークショップのご相談も承っております。ご興味のある方は、下記からお気軽にご相談ください。
承継に向けた対話の土台を引出す!
ストーリー年表のご相談はこちら

記事監修
ICF認定PCCコーチ/代表取締役社長 小泉 領雄南
2011年にGMOペイメントゲートウェイに入社。2016年、子会社の執行役員 経営企画室長に就任し、2020年の上場を経験。 早稲田大学MBA在学中にコーチングを本格的に学び、翌年メタメンターを設立。 国際コーチング連盟(ICF)が認定するPCCコーチ(500時間以上の豊富な実績が求められるICFの専門資格)として、MBAホルダーおよび上場企業の経営企画経験、そして元ICFジャパン運営委員としての知見を活かし、事業承継に関わる経営者・後継者向けコーチングを専門におこなうほか、コーチ・カウンセラー向けのウェルビーイング診断やCRMサービスの開発にも取り組む。