目次
企業の成長には、従業員の能力を引き出し、組織全体の変革を促す組織開発が欠かせません。組織開発の手法の一つとして「コーチング」が注目されています。
しかし、コーチングを導入しても期待した成果が得られなかったり、組織開発との関連性が見出せなかったりといった課題もあるのが現状です。
そこで本記事では、コーチングと組織開発の基本概念から、具体的な手法、導入のポイント、成功事例まで紹介します。
「コーチングを導入した組織開発の効果」を可視化するためには、メタメンター株式会社が提供する「ウェルビーイング」診断がおすすめです。ウェルビーイング診断は、従業員のウェルビーイングを、心理的・社会的・身体的の3側面から統合的に評価、数値化します。
診断履歴が残るため、コーチングの前後における変化など、コーチング効果を可視化できます。ウェルビーイング診断は無料で利用できますので、下記から気軽にお試しください。
コーチングと組織開発の関係性とは?

企業の成長や変革を促進するうえで、コーチングと組織開発は密接に関係しています。
コーチングが個人の成長を支援する手法であるのに対し、組織開発はチームや企業全体の変革を目的としています。組織が持続的に成長するためには、制度や仕組みの導入だけでなく、従業員一人ひとりが自律的に考え行動する文化の醸成が不可欠です。
コーチングは、従業員が自身の強みや課題を認識し、主体的に行動目標を設定・実行するプロセスを支援します。個人の自律性が向上し、組織のビジョンや目標に対する理解と共感が深まった結果として、従業員のエンゲージメントやパフォーマンスが向上し、組織全体の生産性向上、ひいては組織開発の目標達成に大きく貢献します。
さらに、目標設定やチームビルディングなど組織開発の取り組みにおいて、コーチングのスキルや考え方は非常に有効です。例えば、チームビルディングのプロセスでコーチングを活用することで、メンバー間の相互理解を深め、より強固なチームを構築できます。
本章では、まずコーチングと組織開発の基本概念を整理し、それぞれの関係性について掘り下げていきます。
コーチングとは?
コーチングとは、対話を通じて個人の思考や行動の変革を促し、目標達成を支援するプロセスです。
コーチングでは、コーチが答えを与えるのではなく、質問や対話を通じて相手の内面にある可能性や強みを引き出し、自己成長を促すアプローチを取ります。
コーチングを網羅的に把握したい方は、下記の記事もぜひチェックしてみてください。

コーチングとは?必要な3つのスキルやメリット、課題まで総まとめ
コーチングとは、個人やグループの潜在能力を最大限に引き出し、目標達成をサポートするための対話のプロセスです。本記事では、コーチングの概念やICFが定める基準、メリットなどを解説します。
記事掲載日:2024年9月2日
組織開発とは?
組織開発とは、組織が抱える課題を解決し、より良い状態へと変革していくための取り組みです。
組織開発の定義は一つではありません。組織開発の対象は、組織全体・部門・部署・個人と幅広く、人と人との関係性など組織の中の「ソフトな面」にも着目して変革を促します。
組織開発では、個人の意識改革や行動変容が組織全体の変革につながると考えられるため、個人の成長を促すコーチングは組織開発と親和性が高く、変革の一環として導入されるケースも多くみられます。
組織の持続的な成長を促すヒントにもつながる「組織開発の基本概念や進め方」を紹介しているので、関心のある方は下記の記事もご覧ください。

組織開発とは?3つの課題や取り組み、推進のポイントや事例など総まとめ
組織開発とは、組織が抱える課題を解決し、より良い状態へと変革していくための取り組みです。本記事では、組織開発の概要やメリット、役立つフレームワーク、推進のポイントなどを紹介します。
記事掲載日:2025年1月28日
コーチングと組織開発は、親和性が高いだけではありません。組織開発においてコーチングは、不可欠な要素です。ここからは、コーチングが組織開発に必要な理由を5つの観点から紹介します。
コーチングが組織開発に欠かせない5つの理由

組織開発において、コーチングが欠かせない理由は、以下の5つです。
- 組織の潜在的な課題を顕在化し、変革のきっかけを生む
- 従業員の声に耳を傾け、組織のエネルギーを高める
- チームの自律性を高め、主体的な行動を促す
- 生産性を向上させ、業務効率と創造性を高める
- 多様な視点を取り入れ、組織の成長を加速させる
コーチングが組織にもたらす本質的な価値を理解することで、自社での導入や活用方法を具体的にイメージしやすくなります。
理由1.組織の潜在的な課題を顕在化し、変革のきっかけを生む
実は、組織のなかには表面化していない課題や感情が数多く存在します。潜在的な課題が放置されると、組織の成長が停滞する要因になりかねません。
そこで、個人が自身の思考や感情を深く掘り下げるプロセスを通じて、無意識に抑え込まれていた意見やアイデアを引き出すのがコーチングの役割です。
コーチングの結果、組織の隠れた課題が明るみに出るとともに、変革の必要性が浮き彫りになり、持続的な成長のための第一歩を踏み出しやすくなります。
理由2.従業員の声に耳を傾け、組織のエネルギーを高める
コーチングは「傾聴」を重視するアプローチです。傾聴とは、相手の話に耳を傾け、理解し、共感を持って受け止めるコミュニケーションの姿勢を指します。
従業員が自分の考えをじっくり話し、その声を組織が真剣に受け止めることで、従業員には「自分の意見が尊重されている」という実感が生まれ、心理的安全性が高まります。
すると主体的に意見を発信しやすくなり、従業員のエンゲージメント向上につながる点がメリットの一つです。
加えて組織内の対話の質が向上すれば、変革のエネルギーも高まり、全員が共通の目標に向かって一体感を持って取り組めます。
理由3.チームの自律性を高め、主体的な行動を促す
コーチングは、一人ひとりの自己認識を高め、自律的な行動を促すものです。従業員はこれを通じて、自身の強みや改善点を理解し、目標設定や問題解決に主体的に取り組むことができます。
例えば、目標達成に向けたアクションプランを自分で立てることで、従業員は「成長を自分の手でつかむ感覚」を得られます。コーチングは、メンバーの内発的な動機付けを促し、組織全体の自律性を向上させる効果が期待できます。
また自律性の高いチームは、指示待ちではなく自ら考えて動くため、組織全体の意思決定がスピードアップし、柔軟な対応が可能です。特に変化の激しいビジネス環境では、自律的な文化の醸成が競争力の強化につながります。
理由4.生産性を向上させ、業務効率と創造性を高める
コーチングは、チームの生産性向上や創造力の強化にも役立つツールです。
コーチングを通じてメンバーは自身の内面に深く向き合い、固定概念にとらわれない自由な発想を促されます。新しいアイデアや解決策が生まれやすくなり、創造性の活性化が期待できます。
また、メンバーが仕事に対する責任感を強め、より効果的な業務の進め方を模索できるよう支援するのもコーチングの一つです。例えばセッションを通じて、タスク管理や時間管理のスキルを磨き、仕事の優先順位を適切に設定する習慣が身につきます。
チーム内でのコミュニケーションが活性化し、協力して目標を達成する文化が育まれることも、生産性向上につながる理由の一つです。
コーチングにより「生産性向上」や「創造的なアイデアの発想力」が高まると、業務の効率化だけでなく新しい取り組みが生まれやすくなり、組織全体のイノベーション推進に役立ちます。
理由5.多様な視点を取り入れ、組織の成長を加速させる
組織開発では一つの視点に偏らず、多様な視点から物事を考えることが大切です。
コーチングを通じてメンバー間で相互にフィードバックし合う環境を整えると、組織の課題解決能力の向上が期待できます。
また、外部のコーチやファシリテーターを活用することで、より客観的な視点を取り入れられ、組織変革のスムーズな推進につながります。特に、多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まる企業では、異なる視点からイノベーションが創出されやすいのでおすすめです。
組織開発に不可欠なコーチングですが、どのような企業に導入するとより効果的なのでしょうか。ここからは、「組織開発にコーチングを導入するべき組織」の主な特徴を紹介します。
組織開発にコーチングを導入するべき組織の特徴
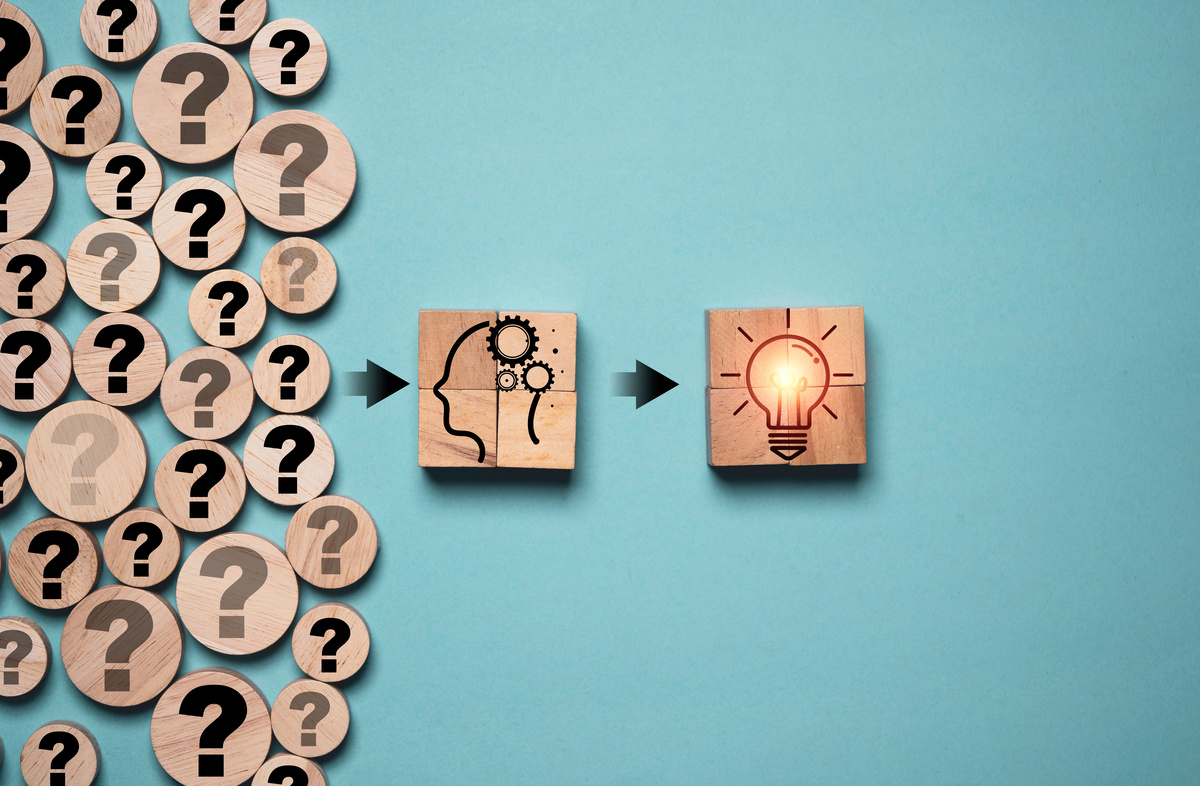
コーチングで組織開発をするべき組織の特徴は、以下です。
【組織開発にコーチングを導入するべき組織の特徴】
| 組織の特徴 | 具体的な課題の例 | コーチング導入で期待できる効果 |
|---|---|---|
| 信頼関係が希薄で、心理的安全性が低い | 不正・ハラスメントの発生、意見が言えない環境 | 傾聴と対話を通じて信頼関係を構築し、透明性のある職場環境を実現 |
| トップダウン型の組織で、メンバーの主体性が低い | 指示待ちが常態化し、従業員が受け身 | 従業員の意識改革を促し、自発的に考え行動する文化を醸成 |
| 本音を言いづらく、オープンな議論ができない | 意見の衝突を避ける傾向があり、会議が形骸化 | 対話の質を向上させ、心理的安全性を高めることで、建設的な議論を促進 |
| 従業員が自分らしく働けず、エンゲージメントが低い | 仕事へのやり甲斐を感じられず、離職率が高い | 個々の価値観や強みを活かす働き方を支援し、仕事への意義を高める |
| 指示待ちの文化が根付いており、自律性が低い | 自発的な問題解決ができず、業務の停滞が発生 | コーチングによる対話を通じて、従業員の責任感と自己管理能力を向上 |
自社の組織に当てはまる課題がある場合は、コーチングを導入することで職場環境の改善や組織の活性化につながる可能性があります。ぜひ取り入れてみてください。
ただ「コーチング」といっても、目的によってさまざまな手法があります。ここからは、コーチングの代表的な手法を5つ紹介します。
目的で使い分け!コーチング手法の5つの種類

コーチングの主な手法は、以下の5つです。
コーチングにはさまざまな手法がありますが、目的や対象に応じて適切な方法を選びましょう。なかでも、生産性向上や組織の一体感を強化できるチームコーチングは押さえておきたい手法です。それでは、ひとつずつ紹介します。
種類1.GROWモデル
GROWモデルは、次の4つのステップで進めるシンプルかつ効果的なコーチング手法です。
| Goal(目標) | 達成したいゴールを明確化する |
|---|---|
| Reality(現状) | 現在の状況や課題を整理する |
| Options(選択肢) | 目標達成のための選択肢を考える |
| Will(意思) | 具体的な行動計画を決定する |
おすすめ活用シーンは、下記のとおりです。
・個人のキャリア目標やスキルアップを支援する
・組織の課題を解決するためのアクションプランを作成する
・新任マネージャーがメンバーの育成に活用する など
GROWモデルのメリットとして、シンプルなフレームワークで誰でも活用しやすく、目標に向かって体系的に思考を整理できる点が挙げられます。行動計画が明確になるので、実行につなげやすい点も特徴です。
種類2.ソリューション・フォーカスト・コーチング
「ソリューション・フォーカスト・コーチング」は、問題の原因に焦点を当てるのではなく「どうすれば解決できるか?」にフォーカスするアプローチです。
課題に対してポジティブな視点を持ち、短期間で具体的な解決策を見出すことを目的とします。
おすすめの活用シーンは、主に下記のとおりです。
・短期間で成果を上げたい(新規プロジェクトの立ち上げ時など)
・すでにパフォーマンスが高いチームのさらなる成長を促したい
・問題志向ではなく、未来志向で解決策を見出したい など
ソリューション・フォーカスト・コーチングは、問題の掘り下げではなく、解決策をすぐに導き出せる点がメリットです。メンバーのポジティブな行動変容を促し、目標達成までのプロセスを短縮できます。
種類3.リーダーシップコーチング
リーダーシップコーチングは、マネージャーや経営層向けのコーチング手法です。リーダーが持つ影響力を活用し、チーム全体の成長を促すことを目的とします。
リーダーシップコーチングでは、個々のリーダーの強みを引き出し、リーダーシップのスタイルを確立するサポートをおこないます。
おすすめの活用シーンを、下記にまとめました。
・経営層やマネージャーの意思決定力を強化する
・リーダーシップスキルの向上を目指す管理職向けの研修を実施する
・組織のビジョンや目標をメンバーに浸透させる など
リーダー自身の成長が組織全体の成長につながり、部下との対話力や影響力を高める効果が期待できるほか、組織の一体感やエンゲージメント向上にも効果的です。
種類4.チームコーチング
チームコーチングは、個人に対するコーチングではなく、チーム全体にアプローチする手法です。チームの相互理解を深め、コミュニケーションを円滑にすることで、生産性向上や組織の一体感を強化します。
おすすめの活用シーンは、主に下記のとおりです。
・チームのパフォーマンスを最大化する
・部署間の連携を強化し、組織全体の成果を高める
・チーム内の対話を促し、相互理解を深める など
チーム全体の協力体制を強化できる点が特徴です。コミュニケーションが活性化し、心理的安全性が高まることで目標達成への共通認識が生まれ、一体感が醸成される効果が期待できます。
チームとしての機能不全を解消し、生産性を向上させる「チームビルディング」と「コーチング」の相乗効果については、下記の記事で紹介しているのでぜひご覧ください。

組織を成功に導く!コーチングとチームビルディング最強活用術:事例とステップ解説
組織を成功に導く「コーチング」と「チームビルディング」について解説。チームの潜在能力を引き出し、組織の成長を加速させる具体的な方法を紹介します。チームの課題を解決し、組織の未来を切り開きませんか?
記事掲載日:2025年2月24日
種類5.エグゼクティブコーチング
エグゼクティブコーチングは、経営層・役員クラス向けのコーチングで、組織のビジョンや戦略策定を支援します。意思決定の質の向上、経営者のリーダーシップ強化が目的の一つです。
おすすめの活用シーンは、主に下記のとおりです。
・経営層が組織のビジョンや方向性を明確にしたい場合
・重要な意思決定のサポートが必要な場面
・経営陣のリーダーシップ強化や自己成長を促したい場合
経営視点での思考を整理し、戦略策定をサポートします。また、経営層が持つ課題を深く掘り下げ、解決策を導く他、組織の長期的な成長につながる意思決定を支援するコーチングです。
組織を成長させる大きな手段の一つであり、平均ROIが700%を超えるとされるエグゼクティブコーチングについては、下記の記事で紹介しています。関心のある方は併せてご覧ください。

平均ROI 788%!エグゼクティブコーチングの効果や導入ステップを紹介
エグゼクティブコーチングは、変化の激しいビジネス界でリーダーシップや意思決定力を強化し、経営者の成長を後押しする手法です。本記事ではその効果や導入ステップ、注意点などを紹介します。
記事掲載日:2023年5月30日
さまざまな手法があるコーチングですが、組織開発に導入する際には押さえておきたいポイントがいくつかあります。ここからは、押さえておきたい5つのポイントを紹介します。
コーチングを組織開発に導入する際の5つのポイント

コーチングを組織開発に導入する際の主なポイントは、以下の5つです。
これらのポイントを押さえ、コーチングで組織開発を成功に導く推進力にしていきましょう。
ポイント1.信頼関係と心理的安全性の確保
コーチングの効果を最大化するためには、コーチと被コーチの間に信頼関係を築くことが不可欠です。
Googleの「プロジェクト・アリストテレス」の研究では、心理的安全性が確保された環境では、メンバーが自由に意見を述べ、積極的に学びや成長に向き合えることが示されました。
【プロジェクト・アリストテレスが発見した「効果的なチーム」の要素】
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 心理的安全性 | チーム内で発言や挑戦をしても、否定や非難されることなく、安心して意見を共有できる |
| 相互信頼 | メンバー同士が信頼し合い、責任を持って仕事を進める |
| 構造と明確さ | 目標や役割が明確で、チームの方向性が共有されている |
| 仕事の意味 | 自分の仕事に価値や目的を感じられる |
| インパクト | 自分の仕事がチームや組織にどのように貢献しているかを理解できる |
研究では「誰がチームにいるか」よりも「チームがどのように協力するか」が、チームの生産性やパフォーマンスの成果に影響すると結論づけられています。
コーチングの場面でも、心理的安全性が確保されると被コーチが本音を語りやすくなり、成長を促す対話が生まれることが共通点です。
参考:Google re:Work – ガイド: 「効果的なチームとは何か」を知る
ポイント2.コーチングの目的を明確化する
組織にコーチングを導入する際は、目的を明確にすることが大切です。「なんとなくコーチングを取り入れる」だけでは効果が曖昧になり、実施後の評価もしにくくなるおそれがあります。
下記の例のように具体的な目的を設定し、目的に応じた手法を選択しましょう。
【目的に適したコーチング例】
| 目的 | 適したコーチングの例 |
|---|---|
| リーダーシップの強化 |
|
| チームの生産性向上 |
|
| キャリア開発・スキルアップ |
|
| 組織文化の変革 |
|
「スキル向上」「エンゲージメント向上」「次世代リーダー育成」など、組織のニーズに応じた明確な目標を設定するのがおすすめです。
コーチング導入の背景や目的を全社的に共有し、関係者の理解を得ることも忘れずに実施しましょう。
ポイント3.適切なコーチの選定
コーチングの効果は、適切なコーチの選定に左右されると言っても過言ではありません。
社内コーチングをおこなう場合と、外部のプロフェッショナルを活用する場合では、それぞれのメリット・デメリットがあります。下記の違いをもとに、活用方法の参考にしてみてください。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 社内コーチ(上司・マネージャーが担当) | ・組織の文化や課題を理解している ・日常の業務に組み込める |
・コーチングスキルが不足する場合がある ・人間関係の影響で本音が出にくいケースもある |
| 外部コーチ(プロフェッショナル) | ・客観的な視点でサポート可能 ・コーチングの専門知識が豊富 |
・コストがかかる ・組織の細かい事情を把握しにくい |
社内コーチを活用する場合は、上司やマネージャー向けのコーチング研修の実施など、スキルの習得や向上の取り組みは不可欠です。
一方で外部コーチを活用する場合は、組織の文化やニーズに合ったコーチを選びましょう。
外部コーチと内部コーチを併用すると、それぞれの強みを補完し効果的なコーチング体制が構築できるのでおすすめです。
ポイント4.コーチングを継続的に実施する仕組みを作る
コーチングは「一度のセッション」で終わるものではなく、継続的な対話のなかで成長を促します。
そのため単発の導入ではなく、定期的にセッションを実施し習慣化するのがポイントです。
【継続性を確保するためのポイント】
・月1回 or 2週間に1回など、定期的なセッションを計画する
・上司と部下の定期的な1on1にコーチングの要素を取り入れる
・個別コーチングだけでなく、チーム全体でのコーチングセッションも導入する など
ポイント5.成果を評価し、フィードバックを活かす
コーチングの導入効果を最大化するためには、KPI(重要業績評価指標)を設定し、成果を定期的に評価します。ただし数値化が難しい場合もあるため、定性的なフィードバックも取り入れましょう。
コーチングの効果を数値で可視化するなら、メタメンターが提供する「ウェルビーイング診断」がおすすめです。
ウェルビーイングとは、心理的、社会的、身体的に満たされた状態を指します。メタメンターのウェルビーイング診断は、従業員の幸福度を心理的、社会的、身体的の3側面から統合的に評価、数値化できるため、コーチングの効果を定量的に可視化できます。
その他の特徴は、以下です。
【ウェルビーイング診断の特徴】
・行動分析学・臨床心理学の研究をおこなっている早稲田大学 大月教授が監修
・学術的根拠があり、信頼できる診断結果
・5分で回答できる直感的なデザイン
・個人も法人も無料で利用できる
大月教授による、ウェルビーイング診断の活用方法を動画でわかりやすく解説していますので、併せてご覧ください。
ウェルビーイング診断を使って継続的にウェルビーイングを測定することで、コーチング施策の長期的な変化や効果の追跡に活用できます。
数字的な裏付けがあることで、コーチングに対する信頼感を高める「ウェルビーイング診断」は、下記のボタンからお気軽に試してみてください。
組織開発の成果を測る指標として使える!
ウェルビーイング診断はこちらコーチングで組織開発に取り組む企業の事例
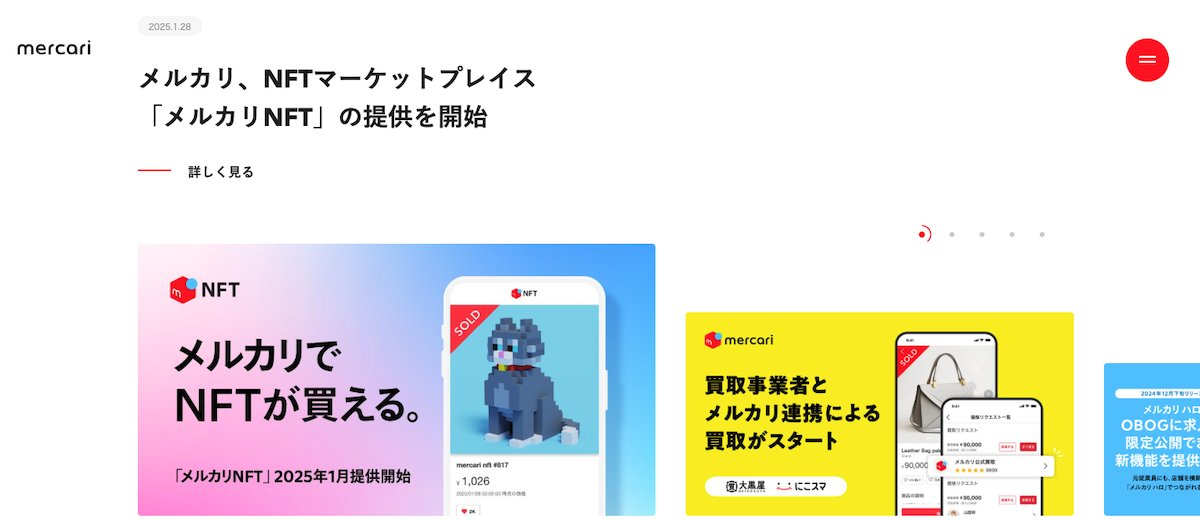
出典:株式会社メルカリ
最後に、組織開発にコーチングを取り入れた企業の事例を紹介します。
メルカリは2022年から正式なコーチングプログラムを導入し、メンバーの個々のパフォーマンス向上を目指しています。
メルカリの「メルカリコーチングプログラム」は、組織と個人の可能性を引き出し、メンバーの成長を促進するために設けられた取り組みです。
【メルカリの主な取り組み】
・「採用に強い」企業から「育成にも強い」企業を目指し、コーチングプログラムを展開
・コーチングを通じて社員が本音で語り合う場を提供し、各自の強みを引き出すことに注力
・コーチ養成プログラムで成長したメンバーが、他者を支援するサイクルを構築
・経営幹部や部門間のコミュニケーションの橋渡しにもコーチングを活用
・2022年の導入以来社員満足度は高く、外部コーチングサービスに匹敵する評価を獲得
コーチングを受けたメンバーからは、「自己理解が深まった」「周囲との関わり方が改善された」との声が多く寄せられています。
メルカリのコーチングプログラム導入は、社員の満足度向上だけでなく組織全体の生産性向上にもつながっています。
参考:社内コーチが語る、Unleashされゆくメルカリの「組織」と「人」の可能性 | mercan (メルカン)
下記の記事では、組織開発に取り組む経営者や人事の方に向けて、コーチングを活用した組織開発の事例や実践方法を紹介しています。従業員の成長や組織開発につながるヒントにもつながりますので、ぜひチェックしてみてください。

コーチングを取り入れた組織文化改革とは?手法や事例を紹介
コーチングを駆使して組織文化を改善する方法を経営者・人事向けに解説。モチベーション向上やコミュニケーション改善に役立つ手法を紹介し、実践を通じて社員と組織の成長を促します。今すぐコーチングで変革を始めましょう。
記事掲載日:2024年7月1日
まとめ:コーチングで組織開発を加速し、チーム力を高めよう!

コーチングは組織開発の際の有用なツールとして、従業員のエンゲージメント向上や自律的な行動を促し、組織全体の生産性向上と創造性の発揮を促す効果があります。
組織の持続的な成長を支援するために、コーチングを戦略的に活用し、より強いチームを育てていきましょう。
「とはいえ、セッション履歴など顧客情報の管理が大変、、、」「チーム内でもっと簡単に情報共有ができたら、、、」という方に向けて、メタメンターでは日本初のコーチング管理ツール「MetaMentor CRM 」を提供しています。
MetaMentor CRMは、従来の表管理ツールや紙では難しかった「一人ひとりに合わせた柔軟なクライアント管理」ができるツールです。
クライアント情報を一元管理し、求める情報にすぐにアクセスできるため、業務効率化につながります。管理作業の削減により空いた時間で、最新のコーチング手法の学習やスキルアップの時間確保も可能です。
無料で登録できて、ウェルビーイングが可視化できる「ウェルビーイング診断」も搭載された「MetaMentor CRM 」についての詳細は、下記をクリックのうえ気軽にご確認ください。

記事監修
代表取締役社長 小泉 領雄南
2011年にGMOペイメントゲートウェイ入社。2016年にGMOフィナンシャルゲート執行役員に就任し、2020年に上場。2021年、早稲田MBA在学中にコーチングに出会い、翌年メタメンター設立。2023年に国際コーチング連盟日本支部運営委員に就任。










